家族の介護が必要かもしれない――。そんなとき、まず考えるべきなのが「要介護認定」の申請です。
要介護認定を受けることで、公的な介護保険サービスを利用できるようになり、介護の負担を大きく軽減できます。
この記事では、要介護認定とは何かから、申請方法、認定の流れ、サービス利用までをわかりやすく解説します。
要介護認定とは?
「要介護認定」は、介護がどの程度必要かを国(市区町村)が判断する制度です。
認定を受けることで、訪問介護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具レンタルなどの介護保険サービスが利用できます。
要介護認定の結果は、以下の7段階に分かれています。
- 非該当(自立):介護保険サービスは使えません
- 要支援1・2:軽度の介護予防が必要
- 要介護1〜5:数字が大きいほど介護の必要度が高い
認定を受けるための申請方法
申請は、お住まいの市区町村(沼田市役所など)の介護保険担当窓口で行います。
本人、または家族、地域包括支援センター、ケアマネジャーなどが代わりに申請することも可能です。
【申請に必要なもの】
- 被保険者証(介護保険証)
- 認印
- 医療機関の情報(かかりつけ医)
認定までの流れ(ステップ別)
① 要介護認定の申請
窓口または郵送で申請を行います。申請書は市役所に置いてあるほか、ホームページからダウンロードできる自治体もあります。
② 調査(訪問調査)
申請後、数日〜1週間以内に市区町村の担当者や委託された調査員が自宅や施設を訪問し、本人の身体状況や生活状況を聞き取り調査します。
【調査内容の例】
- 食事・入浴・排せつなど日常生活の自立度
- 認知症の症状の有無
- コミュニケーションの可否
③ 主治医意見書の提出
市区町村がかかりつけ医に「主治医意見書」の作成を依頼します。
これは医師が、本人の病状や身体機能、認知症の有無などを医学的に評価するものです。
④ コンピューターによる一次判定
訪問調査の内容をもとに、国が定めたソフトで一次判定を行います。
⑤ 介護認定審査会による二次判定
一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家による委員会)が審査し、最終的な認定が決まります。
結果通知と認定の有効期間
申請から約30日以内に、結果が郵送で届きます。
認定結果には、要介護度と「どのサービスがどれくらい使えるか」の限度額も書かれています。
【認定の有効期間】
- 初回認定:原則6か月
- 更新:認定更新申請を行えば延長可能(12か月〜24か月)
要介護認定を受けた後の流れ
認定が出たら、実際に介護保険サービスを利用するために次の手続きを行います。
① ケアマネジャーの選定
要支援の場合は地域包括支援センター、要介護の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが支援を行います。
② ケアプランの作成
ケアマネジャーが本人・家族と相談しながら、サービスの内容や頻度を計画(ケアプラン)にまとめます。
③ サービス提供事業所との契約・利用開始
ケアプランに沿って、訪問介護やデイサービスなどの事業所と契約し、サービスがスタートします。
よくある質問(Q&A)
Q. 要介護認定の更新はいつすればいいの?
A. 有効期限の60日前から更新申請が可能です。ケアマネジャーが手続きのサポートをしてくれるので安心です。
Q. 一度「非該当」とされた場合はもう申請できない?
A. 状況が変われば再申請可能です。転倒や病気などで状態が悪化した場合は、再度申請を検討しましょう。
要介護認定を受けることで、さまざまな公的サービスを使えるようになり、介護する家族の負担を減らす大きな助けになります。
申請から利用開始までの流れは複雑に感じるかもしれませんが、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談すれば、スムーズに進めることができます。
介護サービスと聞くと、施設への入所などのイメージがあるかもしれませんが、自宅での生活を支えるサービスもたくさんあります。日常生活の中で、困ったな、助けてもらえたらいいな、ということがありましたら一度相談してみてください。
大誠会グループでも要介護認定のご相談から、実際の介護サービス提供までしっかりサポートしています。「どこに相談したらいいかわからない」と感じたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
\お問い合わせはこちら/
医療法人大誠会内田病院 地域医療連携室
TEL)0278-24-5329
▶ 詳しくはこちら:医療法人 大誠会 介護サービス
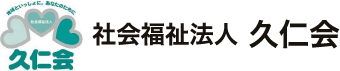





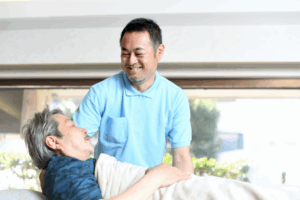



コメント