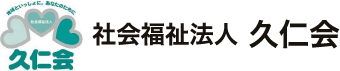「特別支援学校の卒業後、うちの子はどこへ進めばいいのだろう?」
「就職?作業所?施設?…選択肢が多くてわからない」
そんな不安を抱える保護者の方は少なくありません。
高校3年生を迎えるころから「進路をどうするか」は、家族にとって大きなテーマになります。
この記事では、特別支援学校を卒業したあとの主な進路と、活用できる福祉サービスの種類や選び方について、わかりやすくまとめました。
将来を考えるうえでの参考にしていただければ幸いです。
◆ 卒業後の主な進路は3つ
特別支援学校(高等部)を卒業したあとの進路は、大きく分けて次の3つです。
① 就職(企業など)
一般就労を目指している場合、就労移行支援などの福祉サービスを活用して、訓練や職場体験を積むケースが多いです。
特別支援学校のキャリア教育とも連携して、地域の企業への実習や面接練習を行うこともあります。
② 福祉的就労(就労継続支援A型・B型)
「いきなり一般企業は難しいけど、働く経験を積みたい」
そんな方には、就労継続支援A型・B型事業所があります。
- A型:雇用契約あり(最低賃金が保証される)
- B型:雇用契約なし(マイペースに働ける)
本人の特性や体調に合わせて、自分のペースで働くことができるのがB型の魅力です。
③ 生活支援中心の施設(生活介護など)
日常生活を充実させたい方には、生活介護という通所施設があります。
ここでは、食事や入浴などの支援のほか、リハビリ・レクリエーション・作業活動などが行われます。
◆ 福祉サービスを活用するための準備
卒業後すぐに福祉サービスを利用できるようにするためには、事前の準備が大切です。
【ステップ1】 相談支援専門員に相談する
福祉サービスの利用には、「サービス等利用計画」が必要です。
これは相談支援専門員が作成してくれます。
【ステップ2】 受給者証を取得する
市町村で「障害福祉サービス受給者証」を申請します。
これがあれば、就労支援・生活介護・グループホームなどの福祉サービスが利用可能になります。
◆ 福祉サービスの一例(群馬県・久仁会の場合)
以下は、実際に沼田市で提供されているサービスの一部です。
● 就労継続支援B型「みんなのジョブセンター」
- 病院清掃・農作業・内職などを中心とした作業活動
- 定員14名、送迎あり
● 生活介護「Ken Ken Club」
- 理学療法士によるリハビリ、温泉入浴、創作活動など
- 重度の方も安心して通える体制
● グループホーム「Viva Vivo」
- 自立を目指す方に、夜間支援付きの住まいを提供
- 家族と同居が難しくなった場合の安心の選択肢
◆ 保護者の不安Q&A
Q. 就職が難しい場合はどうしたらいいですか?
A. 無理に就職にこだわる必要はありません。就労支援B型や生活介護で、社会とのつながりを持ちながら過ごすことも立派な選択です。
Q. 一人暮らしが心配です…
A. グループホームやショートステイを体験しながら、少しずつ自立をサポートしていく方法もあります。
Q. うちの子に合う施設を見つけるには?
A. 見学や体験利用ができる施設が多いので、複数の事業所を見て比べてみることをおすすめします。
◆ まとめ|“卒業”はゴールではなくスタート
特別支援学校の卒業は、子どもにとっても保護者にとっても「一区切り」。
でも、同時に地域で生きていくための新しいスタート地点でもあります。
焦らず、でも早めに動き出すことが、納得できる選択につながります。
「うちの子にはどんな選択肢があるだろう?」そんなときは、ぜひ地域の相談支援機関や福祉サービス事業者に声をかけてみてください。
\お気軽にご相談ください/
みんなのための障がい支援センター
障がい福祉に関するご相談やサービスのご利用計画を専門員が無料で対応します
TEL:0278-25-8311
Mail:minnanotameno@kyujinkai.com
▶ おすすめリンク
- 久仁会 障がい福祉サービスの紹介ページ
- 久仁会 相談支援センター(問い合わせ)