介護保険制度では、介護が必要な状態に応じて「要支援1・2」「要介護1~5」と区分されます。
最初に「要支援1」と認定された場合、その方はまだ自立度が高く、生活に少しサポートが必要な段階です。しかし、病気や体力の低下などにより介護度が上がることがあります。
では実際に、介護度が上がるとどのような変化があるのでしょうか?ここでは、メリット・デメリットをわかりやすく解説していきます。
介護度が上がると利用できるサービスが増える(メリット)
介護度が高くなると、介護保険で利用できるサービスの範囲や内容が広がります。
たとえば、要支援1の方が受けられるのは「介護予防サービス」が中心で、利用できる内容には限りがあります。デイサービスや訪問介護も、あくまで“予防”が目的であり、生活支援がメインです。
しかし、要介護1以上になると「介護サービス」が使えるようになります。これにより、以下のようなサポートを受けやすくなります。
- 訪問介護(ホームヘルパー)
調理や掃除などの生活援助だけでなく、入浴や排泄の介助といった身体介護も利用可能になります。 - デイサービス
入浴介助や機能訓練が充実し、利用時間も長めに確保できる場合があります。送迎付きなので、ご家族の負担軽減にもつながります。 - 福祉用具のレンタル
手すりや歩行器、ベッドなどを借りやすくなり、在宅生活の安全性が向上します。 - ショートステイ
家族が旅行や休養をとりたいときに、一時的に施設に預かってもらえる制度を活用しやすくなります。
このように、介護度が上がると「できないことを補うための支援」が拡充されるため、安心して生活できる環境が整いやすくなるのです。
介護度が上がることで生じる負担(デメリット)
一方で、介護度が上がることには注意点やデメリットもあります。
1. 本人の心身の状態が低下している
介護度が上がるということは、日常生活の中でできないことが増えているということです。
「もう一人ではできない」と感じる場面が増え、本人が自信を失ったり、意欲が下がってしまうケースも少なくありません。
2. 利用者負担が増える可能性
介護度が上がるとサービス利用の上限額(支給限度額)は増えますが、その分たくさん利用すると自己負担額も増えることになります。
例えば、要支援1の限度額は約5万円程度ですが、要介護1になると約17万円ほどに上がります。1割~3割の自己負担でも、回数を多く使えば費用は大きくなるため、家計への影響が出る場合もあります。
3. 家族の介護負担が重くなる
介護度が高くなるにつれて、家族が担う役割も増えていきます。
特に在宅介護の場合、食事・入浴・排泄などのサポートが必要になれば、家族の体力的・精神的な負担も大きくなります。
介護度が上がっても前向きにとらえる工夫
介護度が上がることは、必ずしも悪いことではありません。
「できないことを補うために、安心してサービスを利用できる段階に進んだ」と考えることもできます。
以下の工夫が、本人や家族の前向きな気持ちにつながります。
- サービスを上手に組み合わせる
デイサービス・訪問介護・ショートステイをうまく活用することで、家族の負担を軽減しつつ、本人も安全に生活できます。 - ケアマネジャーに相談する
介護度に応じた最適なサービス利用計画を立ててくれるため、「どのサービスをどれくらい使えばいいか」が明確になります。 - 本人の得意なことを続ける
「できなくなったこと」ではなく「まだできること」に目を向け、趣味や軽い運動を続けることで心身の活力を保てます。
私たち 大誠会グループでは、群馬県沼田市を中心に、介護保険サービス・障害福祉サービスを幅広く提供しています。
- デイサービスでは、入浴やリハビリ、季節の行事を通じて、心と体の健康をサポート。
- ショートステイでは、ご家族の介護負担を軽減しながら、安心して過ごせる環境を提供。
- グループホームや特別養護老人ホームでは、専門スタッフが24時間体制で生活を支援。
- 障害者支援事業も展開し、年齢や障害の有無に関わらず、その人らしい暮らしを大切にしています。
「介護度が上がったから心配」「この先どうしたらいいのか不安」という方も多いと思います。そんな時こそ、私たちが一緒に考え、寄り添いながらサポートいたします。
▶ 詳しくはこちら
まとめ
介護度が上がると、利用できるサービスが増え、安心して生活を続けられるメリットがあります。
一方で、本人の体力低下や費用負担、家族の負担増といったデメリットも伴います。
大切なのは「介護度の変化を前向きにとらえ、必要な支援をうまく活用すること」です。
要支援1から始まっても、その後の生活の工夫やサービスの利用次第で、本人も家族も無理のない暮らしを続けていくことができます。
\ お困りの方はお気軽にお問い合わせください /
医療法人大誠会内田病院 地域医療連携室
TEL)0278-24-5329
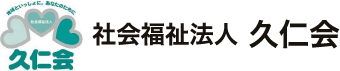




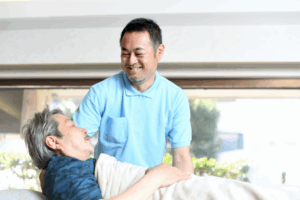




コメント