高齢化が進む現代、誰にとっても他人事ではなくなってきた「認知症」。厚生労働省の推計によれば、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると言われています。大切な家族が認知症と診断されたとき、どのように向き合っていけばよいのでしょうか。この記事では、認知症の基本知識から、ご本人・ご家族が笑顔で暮らすためのヒントまでをご紹介します。
認知症とは?
認知症は、加齢に伴って起こる単なる「物忘れ」とは異なり、脳の病気などが原因で記憶・判断・理解などの認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態を指します。代表的なタイプとして、以下のようなものがあります。
- アルツハイマー型認知症:最も多いタイプ。脳の神経細胞が徐々に壊れていく。
- 脳血管性認知症:脳梗塞や脳出血などが原因で発症。
- レビー小体型認知症:幻視やパーキンソン症状が現れることも。
- 前頭側頭型認知症:感情や行動面の変化が強く出やすい。
認知症のサインに気づく
早期発見が、その後の生活の質に大きく影響します。
以下のような変化に気づいたら、かかりつけ医や専門医に相談しましょう。
- 会話が噛み合わなくなる
- 財布や鍵など、物をよくなくす
- 同じ話を何度も繰り返す
- 日付や場所がわからなくなる
- 急に怒りっぽくなる、閉じこもりがちになる
ご本人が穏やかに暮らすための工夫
認知症と診断されても、すぐにすべてができなくなるわけではありません。
本人の「できること」を尊重し、暮らしやすい環境を整えることが大切です。
生活環境を見直す
- 家の中の段差をなくす
- 見やすい場所に時計やカレンダーを設置する
- 名前や用途を書いたラベルを貼る
日課をつくる
毎日のリズムを作ることで、不安や混乱を和らげられます。
散歩・食事・テレビ体操など、日常に「繰り返し」を取り入れてみましょう。
人とのつながりを大切に
地域の認知症カフェやデイサービスなど、他者との交流は刺激にもなり、孤立を防ぐ効果もあります。
家族ができるサポートと心構え
否定せず、受け入れる姿勢
「違うでしょ!」「なんで覚えてないの?」と責めても、本人を傷つけ、混乱させてしまいます。
本人の言動を肯定し、「一緒に考えようね」と寄り添う姿勢が大切です。
介護者自身の負担軽減
家族がひとりで抱え込まないように、介護サービスや支援制度をうまく活用しましょう。
利用できる支援サービス
認知症初期集中支援チーム
沼田市を含む多くの自治体では、医師や保健師などの専門職がチームを組み、本人や家族に対する支援を行っています。
地域包括支援センター
介護に関する相談窓口。認知症に関する相談や、必要なサービスの紹介など、幅広く対応しています。
介護保険サービス
要介護認定を受けると、訪問介護・通所介護(デイサービス)・ショートステイなどのサービスが利用できます。
地域の福祉施設の取り組み
群馬県沼田市を拠点とする大誠会グループでは、認知症に関するさまざまな支援を行っています。
認知症疾患医療センター内田病院では、診断・治療・家族支援・地域連携を担っており、物忘れ相談も対応しています。その他、認知症の方とそのご家族を支える施設やサービスを広くご提供しています。
ご本人の「その人らしさ」を大切にした関わりを大切にしています。
家族向けの相談や支援も行っており、介護に悩む方の心強い味方となっています。
▶ 詳しくはこちら
笑顔で過ごすために大切なこと
認知症は決して「終わり」ではありません。
早めに気づき、理解し、周囲が支えることで、本人も家族も前向きに生活を続けていくことができます。
焦らず、無理せず、笑顔を忘れずに——。
困ったときは地域の支援や福祉施設に相談し、ひとりで抱え込まないことが大切です。
「その人らしく」生きることを、周囲みんなで応援していきましょう。
\ お困りの方はお気軽にお問い合わせください /
医療法人大誠会内田病院 地域医療連携室
TEL)0278-24-5329
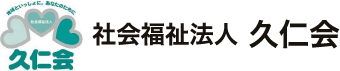
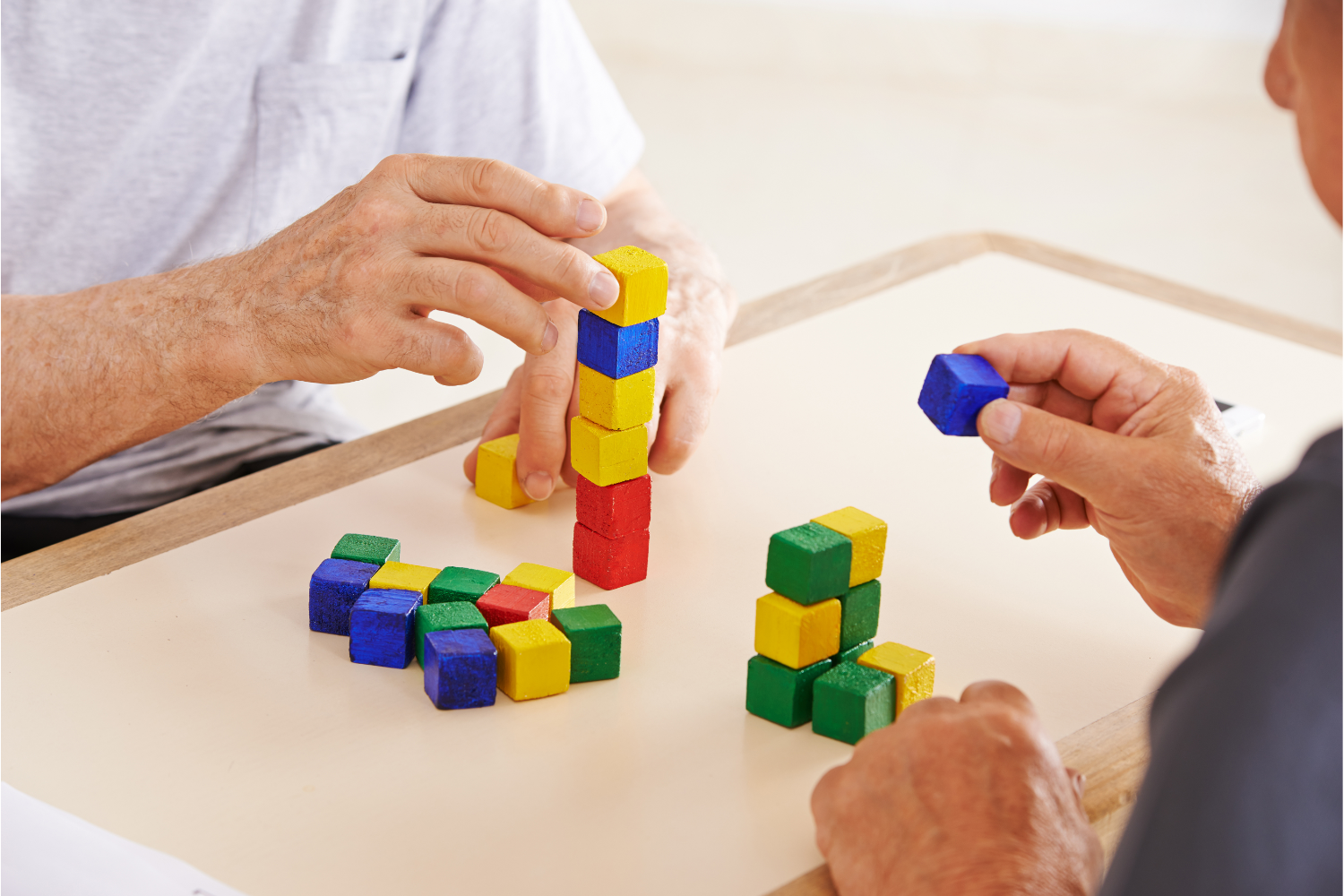




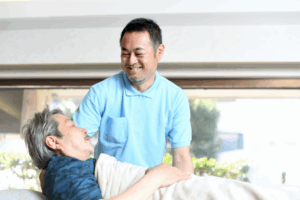



コメント